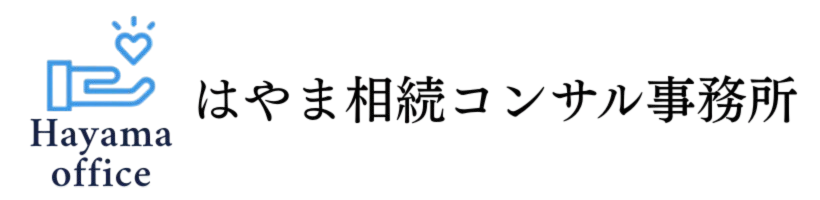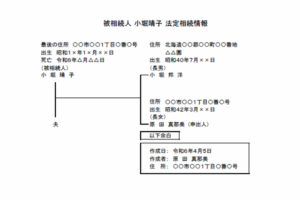相続財産の範囲は思ったより広い
税理士とのやり取りについての記事を書いていて思い出したことがあります。
それが給付金、還付金、未払金に関する失敗談です。
この話には「被相続人の死後、被相続人に関して発生する給付金、還付金、未払金は基本的に相続財産として計上される」という前提条件があります。
では、実際の相続でどんなことがあったのかを書いていくことにします。
①各種給付金
母は亡くなる前の年に持病の肺炎が悪化し、自宅にいる時は酸素濃縮器と呼ばれる機械を使うようになりました。
酸素濃縮器を使うには電気代がかかるため、道から酸素濃縮器の使用にかかる電気料金の助成を受けていました。
助成金は前年1月~12月の分を翌年初めに申請する仕組みだったため、振り込まれたのは母が亡くなった半月後でした。
また、母は住民税非課税世帯だったため、住民税非課税世帯に対する給付金の受給対象者でもあったのですが、この給付金も母が亡くなった後に振り込まれたため、税理士から根拠になる書類を提出するよう言われました。
ただ、私は申請書はおろか、在宅酸素については資格証明書のようなものも破棄してしまっていたため、代わりに制度について書かれているサイトを見つけて税理士にURLを教え、それを見てもらった上で手続きしてもらいました。
なお、通常、給付金が振り込まれる前に通知書が届くと思いますが、うちの場合、母が亡くなった後に振り込まれた給付金や還付金の通知書が届かなかったため、上記の対応をすることになりました。
もし通知書が届いていれば、通知書を提出すれば大丈夫です。
通知書が届かなかった理由については後述します。
②高額療養費の還付
母には持病が複数ありました。
医療費は1割負担でしたが、月に2~3の診療科に定期的に通院して薬ももらっていたため、毎月の医療費が自己負担の限度額を超えていました。。
このため、最初から限度額適用認定証の交付を受けており、自身で手続きすることなく、毎月高額療養費の還付を受けていました。
高額療養費の場合、支給日の数日前に圧着はがきの通知書が届きますが、実際の受診日から2~3ヶ月遅れで届くんですよね。
母が亡くなったのは令和6年3月上旬、その後支払われた高額療養費は令和5年12月~令和6年3月の4回ありましたが、令和5年12月の分は私が破棄してしまっていました。
まさか、前年の通院に対しての高額療養費まで細かくチェックされることはないだろうと思ったので。
そうしたら、被相続人が亡くなった後に振り込まれた還付金は、発生原因が何ヶ月前のものであっても確認が必要となることが判明。
慌てて、市役所に令和5年12月の通知書を再発行してもらう事態に。
③介護保険と後期高齢者医療の還付
介護保険や後期高齢者医療の被保険者が亡くなると、保険料の再計算が行われます。
亡くなった時点で支払うべき保険料を計算して、払いすぎている場合は還付されます。
そして、当然のことですが、還付される保険料は被相続人の死後に振り込まれるため、これも収入としてカウントしなければなりません。
入出金明細を見れば還付金だとわかることも多いのですが、税理士からは還付通知書などを提出するよう言われます。
後日税務署から突っ込まれた時、根拠になるものがないと説得力に欠けるからではないかと思います。
うちの場合は後述する理由により還付通知書が届かなかったため、市役所に再発行してもらいました。
④光熱費の未払分
他には、母が亡くなる以前の使用期間の光熱費の請求書や検針票も必要と言われました。
契約者は母でしたが、私も同居しており、光熱費には私の利用分も含まれているため、光熱費まで母の相続財産としてカウントされるとは思っていなかったんですよね。
検針票の類は、ちょっとするとすぐたまってしまうため、母が元気だった頃からの風習で、口座から引き落とされたことを確認した後に破棄していました。
今はWebで使用量や料金の確認ができるところも増えましたが、ガスと電気についてはサイトのログインIDが母の名前や誕生日をもとにしたものだったため、そのまま使うことに抵抗があり、契約の名義変更と同時に母のアカウントを削除して、新しく自分のアカウントを作り直したんですよ。
当然のことながら、母のアカウントを削除すると同時に過去の使用量や料金の確認はできなくなりました。
ちなみに、水道料金は、毎月マンションの管理会社がポスト投函していく管理費等の請求ハガキに載っていたのですが、こちらも引き落としを確認したら破棄していたため、使用期間や金額を立証するものがなく、光熱費の未払分がない前提で相続税の申告をしてもらいました。
通知書が届かなかった理由
母は生前いろいろな通販を使っており、母宛のDMがよく届いていたんですよ。
亡くなった後もDMが届くのが嫌だったため、不要な郵便物に「本人死亡のため返送します」と朱書きして返送していたら、その後保険会社や役所から届いた母宛の郵便物まで差出人に返送されていたことが後に発覚。
調べてみたら、故人宛の郵便物は、受取人が死亡した事実を郵便局が認識した時点から配達されなくなり、郵便物は差出人へ返送されるそうです。
そうであれば、保険会社や役所には、母が亡くなったことも、相続人が私であることも申告しているのだから、私宛に送ってもらえれば受け取れたのにと思います。
ちなみに、母が亡くなった翌月からは、母に関する還付金は相続人である私の口座に振り込まれています。
まとめ
今回お伝えしたいことは、この3点に尽きます。
- 被相続人の口座に振り込まれたり、口座から引き落とされたりするお金に関する資料は最低半年程度保管しておく
(給付金や還付金の通知書、受給資格を証明する書類、保険金の支払通知書、光熱費の請求書など) - 被相続人が亡くなった後に振り込まれたり引き落とされるお金に関する資料についても、相続手続きが終わるまでは絶対に処分しない
- 光熱費などのWebサービスのアカウントは、可能であれば相続手続きが終わるまでそのままにしておく
(難しい場合は画面のスクリーンショットを撮ったり、プリントアウトするなどしておく)
私の場合、思い切りのよさが災いした形になってしまったのですが、お金のからむ書類についてはもっと慎重になるべきだったと痛感しています。
このブログを読んだあなたは、私と同じ失敗をしないようお気をつけ下さいね。