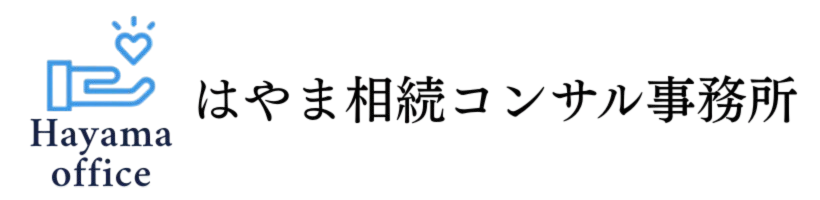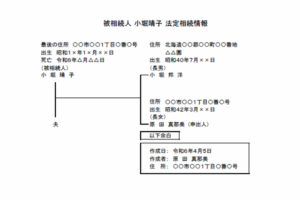「後見人が必要です」と言われる前に知っておきたいこと
「親が認知症になったら、通帳は誰が管理するの?」
「障害のある子どもが成人した後、親が代わりに契約できるの?」
こうした疑問や不安は、家族の将来を考える時に誰もが一度は抱くものです。
特に、本人の判断能力が低下していたり、もともと十分でない場合には、「成年後見制度」の利用が必要になることがあります。
でも、制度の内容をよく知らないまま「後見人をつけてください」と言われるがままに従ってしまうと、「こんなはずじゃなかった」と後悔するケースも少なくありません。
この記事では、後見人が必要になる具体的な場面や制度の種類、そして家族ができる備えについて、わかりやすく解説します。
後見人が必要になる具体的な場面
こんな時に後見人が必要になることがあります。
高齢者の場合
- 認知症などにより判断能力が低下し、財産管理や契約行為が困難になった時
- 高齢者名義の不動産を売却したいが、本人の意思確認ができない時
障害のある子どもの場合
- 成人した子ども名義の預貯金を親が管理しようとした際、金融機関から「本人に判断能力がない」と判断された時
- 親族が亡くなり、子どもが相続人になったが、遺産分割協議に参加できない時
成年後見制度の種類
成年後見制度には法定後見と任意後見がありますが、上記のようなケースでは、ほとんどの場合、判断能力が既に低下しているため法定後見が利用されます。
違いを簡単にまとめたのが下の表です。
なお、法定後見には、判断能力の程度に応じて補佐、補助という段階もありますが、ここでは省略します。
| 項目 | 法定後見 | 任意後見 |
|---|---|---|
| 判断能力の有無 | 判断能力が衰えた後 | 判断能力が衰える前 |
| 利用の方法 | 家庭裁判所へ申立て | 本人と受任者が公正証書で契約 |
| 効力発生のタイミング | 家庭裁判所が後見開始の告知を行う | 判断能力が衰えた後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任 |
| 後見人の選任者 | 家庭裁判所 | 本人または親権者 |
| 後見監督人の選任 | 必要に応じて選任 | 必ず選任 |
| 後見人との関係 | 約8割が専門職(弁護士・司法書士など) | 親族など、信頼できる人を選べる |
| 後見(代理権)の範囲 | 財産管理と身上監護(医療に関する契約、施設入所契約など) | 任意後見契約で定めた範囲すべて |
| 後見人の報酬 | 家庭裁判所が決定(毎月発生) | 契約で自由に定められる ただし監督人の報酬は家庭裁判所が決定(毎月発生) |
| デメリット | 資産運用、生前贈与などの制限 途中でやめられない など | 次の後見人の準備が必要 取消権がない など |
法定後見人がついた後に起こること
法定後見の場合、家庭裁判所はおよそ8割の確率で専門職(弁護士・司法書士など)を後見人に選任します。
後見人がつくと、本人(被後見人)の財産の保護が最優先されます。
その結果、家族が「本人のために」と思って行う支出でも、後見人が「不要」と判断すれば認められないことがあります。
具体的には次のようなことが起こります。
- 本人が元気な頃に「孫に生前贈与したい」と言っていたが、「財産を減らす行為」として認められない
- 元本保証のない投資信託や株式投資は「リスクがある」として認められない
- 自宅を売って施設費用に充てたい場合、家庭裁判所の許可が必要だが、必ずしも許可が下りるとは限らない
- 一度後見が開始されると、本人が亡くなるまで原則としてやめることができないため、後見人や、後見監督人に対する報酬が、本人の亡くなるまで発生することになる
後見の申立てのきっかけは預貯金の引き出しや相続手続きなど、一時的な目的であることが多いのですが、目的を達成したり、後見の必要がなくなっても利用を終了できないことが問題視されています。
こうした背景もあり、法定後見の利用率は認知症高齢者の約4%にとどまっています。
家族ができる対策とは?
法定後見を「使わなくて済むようにする」ことが、最も有効な対策です。
以下のような準備をしておくことで、本人の意思や家族の思いを反映しやすくなります。
- 本人と受任者(信頼できる人など)が任意後見契約を結ぶ(主に高齢者向け)
・判断能力があるうちに、信頼できる人と契約を結ぶ
・公証役場で任意後見契約公正証書を作成
契約内容には、財産管理の範囲や医療・介護に関する意思などを明記する
・判断能力が低下したら、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申立て
なお、障害のある方でも、意思表示ができれば任意後見契約は可能です。 - 親権者が任意後見契約を結ぶ(障害のある子ども向け)
・子どもが未成年のうちに契約
・父母どちらかが何らかの理由で任意後見人になれなくなった場合に備え、
①父の親権を使い、母と任意後見契約締結
②母の親権を使い、父と任意後見契約締結
というように、複数の契約をしておく
・将来に備え、親の次の任意後見人候補も探しておく - 遺言書を作成する(相続人に高齢者や障害のある子どもがいる被相続人向け)
・認知症の高齢者や障害のある子どもが相続人になる場合、遺産分割協議ができない
・遺言書があれば、遺産分割協議を行わずに遺言の内容に従って分配できる - 家族で話し合いをしておく
将来の支援体制や財産管理について、家族間で共通認識を持つために
・誰が後見人になるか
・本人の希望する生活や医療・介護の方針
・財産の使い方や相続の分配方法
について話し合いをするようにする
「後見人が必要になる時」は突然やってきます。
その時に慌てないよう、今からできる準備をしておくことで、家族の安心、ひいては本人の尊厳を守ることができます。