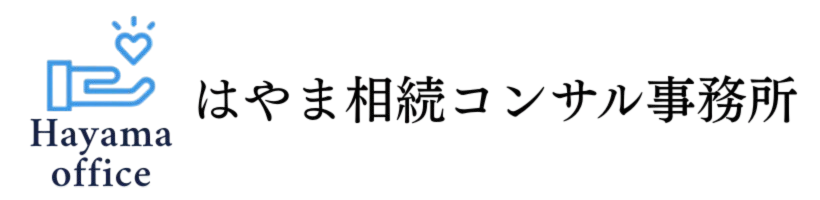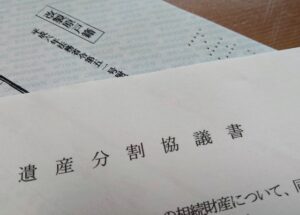親なきあと問題とは?
私はFP(ファイナンシャル・プランナー)の資格を取得した後、「親なきあと問題」に特化した事務所を立ち上げようと考えていた時期がありました。
「親なきあと問題」とは、障害のある子どもを持つ親が亡くなった後、その子の財産管理や生活支援をどうするか、という問題のことです。
現在この問題について学び直しているのですが、今回は我が家の実体験を通して「親なきあと問題」の難しさについてお話ししたいと思います。
家族と不動産を共有したら…
障害のある子どもの財産管理について、何の対策もせず、健常者と同じように行ってしまうと、後々の管理が大変になってしまう場合があります。
その一つが不動産の共有です。
私の兄には中度の知的障害があり、財産管理を自分で行うことは難しく、日常生活も支援が必要な状況です。
父は約35年前、実家のマンションを購入した際、持分を父・母・兄それぞれ3分の1ずつに設定しました。
私は既に家を出ていたため、持分はありませんでした。
5年ほど前から、私は母が亡くなった後、小樽の実家を売却し、札幌へ引っ越す計画を立てていました。
8年前に亡くなった父の持分は既に私が相続、母の持分も最終的に私が相続することは決まっていましたが、兄の持分がそのままだと、私が3分の2、兄が3分の1を所有する形となります。
この場合、実家を売却するには兄の同意が必要になります。
兄は4年前に後志(しりべし)管内の施設に入所し、今後家族と同居する可能性も低いと判断されました。
幸い、兄には一定の判断能力があるため、わかりやすく説明すれば理解はしてもらえるのですが、売却の手続きの時に施設まで行き来するのは距離的に大変だと思いました。
そこで、施設に入所する前に、兄の持分を私に贈与してもらう契約を結んで持分移転を行い、母の持分を相続した後は私一人の所有となったため、単独で実家を売却することができました。
マル優を使った定期貯金を継続しようとしたら…
マル優とは「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」の通称です。
預貯金の元本350万円までの利子が非課税になる「マル優」と、国債と地方債の額面350万円までの利子が非課税になる「特別マル優」がありますが、我が家で利用していたのは「マル優」の方です。
父の生前から、兄名義で郵便局の福祉定期貯金を預け入れていました。
この貯金は1年満期で、自動継続の取扱がないため、満期を迎える都度、預け直しの手続きが必要です。
父が亡くなった後も毎年預け直しをしていましたが、手続きに行くのはいつも母のみ。
兄は仕事や就労継続支援事業所に行っていた関係で、郵便局の窓口が開いている時間に手続きに行くことができず同行していませんでした。
ある年のこと。
母の入院中に満期を迎えたため、私が代わりに預け直しをすることになり、通帳、印鑑、障害基礎年金の証書を持って近所の郵便局へ行きました。
母が行った時は、これだけで手続きできていたようです。
でも、私が行った時は兄を連れてくるか、兄に書いてもらった委任状を持ってきてもらわなければ手続きできないと言われました。
おそらく、本来は母が行った時も同じ手続きが必要だったものの、顔見知りということもあり大目に見てもらえていたのでしょう。
結局、この時は帰宅した兄に事情を説明し、郵便局でもらってきた委任状の必要項目を記入してもらって、後日預け直しをしました。
対策の重要性
おそらく、父には「自分が亡くなったあとも、兄がお金に困らないように」、そして「健常者と同じように扱うことが平等である」という思いがあったのだと思います。
しかも、当時は「親なきあと問題」という言葉もなく、障害のある子どもの財産管理の方法を間違えると、将来的にどんなリスクを伴うか、なんてわからなかったはずです。
実際、私も自分がFP事務所設立に向けて勉強して初めてわかったくらいですから。
幸いにも、我が家の場合はわかりやすく説明すれば理解してもらえるので、不動産の持分移転も定期貯金の預け直しもできましたが、もし兄が重い障害を持っており、意思の疎通ができなかったら、家族の希望する手続きを行うことは不可能でした。
同じように、子どもの障害が重く、判断能力が不十分だったら、親御さんの希望通りに財産を管理することはできません。
対策の一例
親なきあと問題に関して、私が考える基本的な対策は次の通りです。
もちろん、その家の状況により変わる部分はありますが。
- 子どもに不動産を持たせない
(不動産の購入時だけでなく、相続で、子どもが意図せず不動産の持分を取得することもないように) - 子ども名義の財産管理では、子どもが自ら手続きしなければならない金融商品は利用しない
(定期預金、国債、証券口座の開設が必要なNISAや投資信託などを利用すると後が大変) - 可能であれば、子どもが未成年のうちに、親権を使って口座やキャッシュカードを作っておく
(キャッシュカードがあれば、必要になった時、親がATMで預金を引き出せる) - 将来子どもに後見人がつく可能性が少しでもある場合は、子ども名義の預金はできるだけ少ない金額にする
(後見人への報酬は子どもの財産額によって変わるため) - 親が亡くなった時、遺産をどう分けるかを決め、遺言書を作成しておく
(遺言書がないと、遺産分割協議をすることとなり、場合によっては後見人をつけなければならなくなる)
いかがでしょうか?
健常者の相続対策とはかなり違いますよね。
でも、自分で財産の管理ができない、障害のある子どもの場合、このくらいしないと思いもよらぬ結末を引き起こすことがあるんです。
ところで、対策の中に「後見人」というワードがちらほら出てきましたよね。
実は後見人についても、知っておいていただきたいことがあります。
でも、長くなるので、後見人については次回書くことにします。