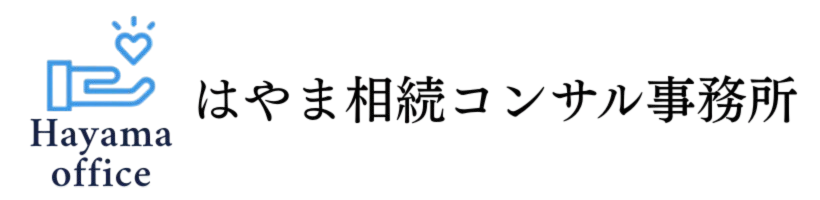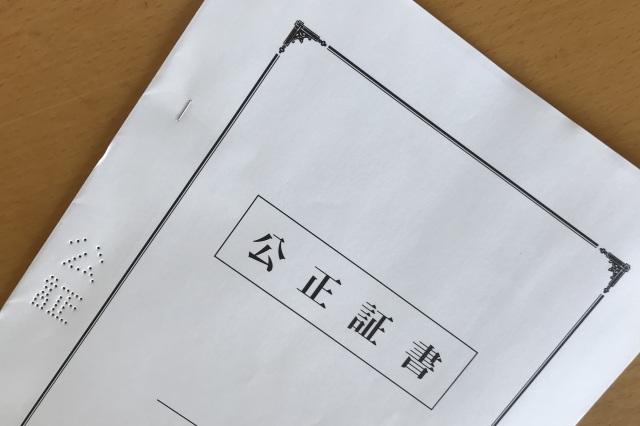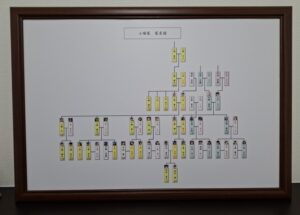今週水曜日(11月19日)の夜に、「『親なきあと』財産プランナー&アドバイザー連絡会」がZoomで開催されました。
私は前日の相続診断士会からの帰宅が遅く、この日の仕事終わりの時点でヘロヘロだったため、残念ながら欠席しましたが、後日アーカイブ動画を見られるようになったため、昨日の昼休みと今日の午前中に視聴しました。
今回のテーマは「公正証書のデジタル化」と「成年後見制度の改正」でした。
私は特に公正証書のデジタル化に関心があったため、この点に絞って書くことにします。
公正証書のデジタル化…何がどう変わる?
公正証書のデジタル化は、2025年10月1日以降、順次指定される公証役場で利用可能になっています。
主なポイントは次の3つです。
- メールによる本人確認の導入
従来は依頼者が公証役場に出向く、または公証人が依頼者を訪問する必要がありました。
これに加え、新たにメールを用いた本人確認が可能になります。 - ウェブ会議(リモート方式)での公正証書作成
従来は対面での作成が原則でしたが、一定の要件を満たし、公証人が相当と認めた場合に限り、ウェブ会議方式での手続きを行うことも可能になります。 - 電子データでの公正証書作成
公正証書は原則電子データで作成されるため、従来の書面交付に加えて、USBメモリへの記録やクラウドからのダウンロードも選択可能になります。
相続の現場でリモート方式は使えるか
リモート方式が使える可能性が出てきたと聞くと、一見、高齢や病気で外出が難しい方には朗報のように思えますが、どうやらそうでもないようです。
連絡会では「親なきあと」お金の相談窓口(今回の主催団体)の代表が、お世話になっている公証人の方にヒアリングした内容が紹介されていました。
公証人の回答は、遺言公正証書や任意後見契約書の作成については、リモート方式が認められない可能性が極めて高いというものでした。
これはその公証人個人の意見ではなく、公証人連合会としての見解のようです。
理由は、画面に映る範囲が限られ、見えない場所で利害関係人が誘導したり脅迫をかけたりしても判別できないため、本人の真意や判断能力の確認が難しいからです。
極端な話、パソコンの横や後ろで誰かが刃物を持って脅していたり、「こう言え」とカンペを出していたりしても、画面越しの公証人にはわかりません。
そうして作られた遺言書に法的な効力を持たせるわけにはいきませんよね。
個人的には「少しでも作成のハードルが下がってほしい」と思っていましたが、安全性を考えると、当面の間は今まで通りの対面作成が続くことになりそうです。
今後のテクノロジー進化に期待
でも、もし将来、Googleマップの撮影に使われるような360°カメラが一般家庭に普及したり、ウェブ会議システムに革命的な進化が起きたりすれば、状況は変わるかもしれません。
いつか、自宅にいながら安全・確実に遺言公正証書や任意後見契約書が作れる未来が来ることを期待したいですね。