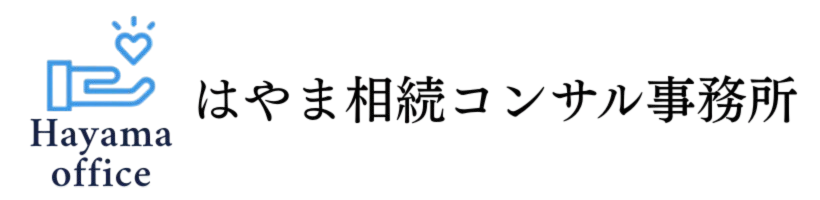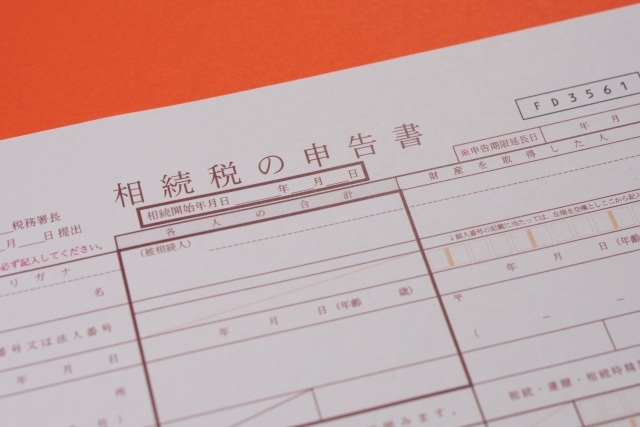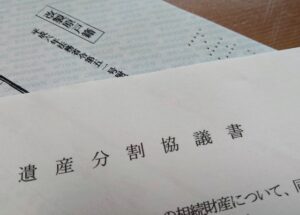なぜ税理士に依頼したのか
母が亡くなった後、私がやらなければならなかった相続手続きは3つありました。
①預貯金の相続、②実家マンションの母の持ち分移転(不動産登記)、③相続税の申告です。
預貯金の相続は、金融機関に電話で教えてもらいながら何とか進め、不動産登記も法務局の予約相談を使って自分でできました。
でも、相続税の申告だけは手を出す前から「これは無理」と思いました。
そう思った理由は次の3つでした。
- 相続税にかかわる税制度が複雑で、制度を理解して正確に書類を作るのは、素人には大変だと思った
- ネットで「税理士じゃない人が作った相続税の申告書は、税務署に厳しくチェックされる」という話を読んでいた
- 申告書を厳しくチェックされ、申告ミスが見つかった場合に来る可能性の高い税務調査が怖かった
(頭に浮かんだのは映画『マルサの女』のような、黒いスーツの人たちがある日突然家に押しかけてくる光景。
私にとっては、警察24時とかでよく見るガサ入れと同等の行為に思えるため、絶対にされたくなかった)
税理士選びで重視したこと
他にも、税理士の腕次第で、本来払わなくていい税金を払う羽目になったり、後から別の税理士に計算し直してもらった結果、還付を受けることになる場合もあると知り「最初から適正に相続税を計算できて、税務調査を限りなくゼロにしてくれる人」にお願いすることにしました。
ネットで探して見つけたのは、関東に本部のある税理士法人。
当時、札幌にも拠点があり、職場から徒歩2〜3分という近さでした。(今は撤退しています)
ホームページを見て、条件もクリアしていると判断し、そこに依頼しました。
実際に依頼してみて
担当は国税出身の税理士。
税理士に国税出身者が多いのは知っていたのでさほど驚きませんでしたが、よく言えば物腰柔らかめ、悪く言えば頼りない印象の人でした。
ただ、税務調査の経験は豊富そうだったので、そのままお願いすることにしました。
その後、やり取りの中で首をかしげたくなることが2つあって、結果的に依頼したことを後悔しています。
1つ目は、税務署に出す書類として「法定相続情報一覧図の写し」は使えないから、戸籍を用意するよう言われたこと。
使える書類だと説明しても「税務署に提出するものですので…」の一点張りでした。
30代後半~40代前半の比較的若い税理士なのに、新しい制度を知らないのか?と思いました。
2つ目は遺産分割についての話です。
母の相続の時の相続人は、知的障害のある兄と私の2人でした。
現在兄は施設に入っていて、兄の手元にある財産の管理は施設に任せているため、遺産はすべて私が相続することで遺産分割協議を済ませていました。
ところが、後から多額の現金が見つかり、税理士にこう言われました。
「最初の遺産分割協議の内容ですと、お兄さんが1円も相続していないため障害者控除が使えず、相続税の総額が200万円近くかかります。
今回見つかった現金の一部をお兄さんに相続させる内容の遺産分割協議をすれば、控除が使えて、税金が安くなります」
兄には既に、親が貯めてきた障害基礎年金があり、一生かかっても使い切れない額になっているため、その提案は受け入れられないと一度断りました。
でも、税理士は「相続税を払うという潔さは認めますが、税理士事務所としてはですね…」と言葉を濁し引き下がろうとはしませんでした。
全部の税理士がそうではないと思いますが、その税理士法人ではおそらく、使える制度はとにかく使って、相続税を減額させることが正義だったんでしょうね。
それがたとえクライアントの意にそぐわないやり方だったとしても。
税理士と話していても平行線のままだったので、最終的に私が折れて、兄にもごく一部を相続させるという内容の遺産分割協議書を追加で作成することに。
最終的に相続税はゼロになりましたが、何とも釈然としない結末でした。
余談ですが。
税理士に相続税の申告を依頼するのと同時進行で、実家マンションの売却をしたため、譲渡所得の申告が別途必要でした。
私は何度も確定申告を自分でやっており、譲渡所得の申告もやったことがあるので、最初から税理士に依頼する気はありませんでした。
でも、11月に相続税の申告書作成がひと段落したら、メールで
別件ですが、売却手続き中の居住用マンションの譲渡所得については、減価償却の計算も関係することから、もしご面倒であれば、弊社で確定申告書の作成を受任させていただくことができますのでご相談頂ければと思います。
と来て、スルーしていたら12月に再度メールで
そういえば、譲渡所得の件は大丈夫でしょうか。
と来たので、そこは強力にプッシュしてくるんかい!と思いつつ
何度かご心配いただいている譲渡所得の件ですが、令和5年分の確定申告書等作成コーナーで試しに入力してみたところ自力でできそうなので(令和6年分の公開が1/6のため、令和5年分で試してみました)、申告の依頼は見合わせます。
と返事してやっと静かになりました。
私の見解
話は戻りますが、ここで法定相続情報一覧図の件についての私の推測を書くことにします。
相続税申告の後、立派な表紙の相続税申告書の冊子が届いたのですが、その中に「被相続人の戸籍」というページがありました。
このページが空白なのはよろしくないということで、私に戸籍を用意させるための方便として税務署を使ったのかもしれないと思いました。
おそらく、その税理士法人では、被相続人の戸籍の束を申告書などと共に綴るという強いポリシーがあったのでしょう。
でも、法定相続情報一覧図を作った後に不要だと思って破棄したくらいですし、必要であれば自分で保管しているので、これって税理士法人の自己満足にすぎないよなと思いました。
人生初の税理士体験はこんな感じで幕を閉じました。
次に機会があった時は、適正に税額を計算してくれるのはもちろんのこと、依頼する側の希望に寄り添ってくれる税理士とつながりたいと思います。