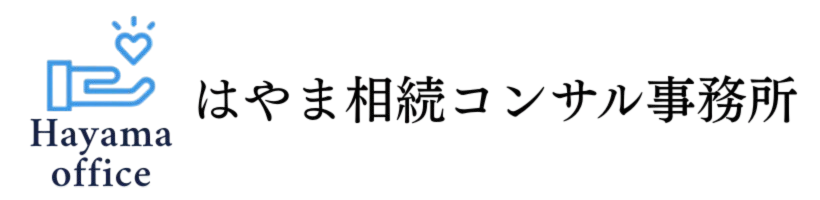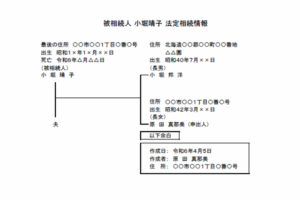以前、「親なきあと問題」について学び直していると書いたことがありました。
実はこのテーマ、将来的に私の取扱業務にしていきたいと考えており、その準備の一環として「『親なきあと』財産アドバイザー®」という資格の養成講座を受講しました。
確認テストにも合格し、現在は資格登録の申請中です。
講座の中では、家族構成や障害のある子どもの状況、保有財産などを踏まえて提案書を作成する方法が紹介されていました。
その事例の一つに「子どもの預金残高を必要以上に増やさないようにし、障害基礎年金の一部を生活費として父親が受け取り、それを原資に生命保険に加入する」というものがありました。
契約者・被保険者は父親、そして受取人は障害のある子ども。
これは、将来もし法定後見制度を利用することになった場合に備えての工夫のようでした。
ここでふと疑問が湧いたんです。
「もし子どもに判断能力がなかった場合、父親が亡くなった時に保険金の請求はできるのか?」と。
生命保険には「指定代理請求制度」がありますが、これは被保険者が生きていて手続きができない場合に使う制度のようなので、被保険者が亡くなった時には使えません。
もう一度テキストを読み返してみると、そこで紹介されていた「生命保険」とは、どうやら「保証期間付終身年金タイプの個人年金保険」のことのようでした。
このタイプは、被保険者の生死に関わらず、5年・10年などの保証期間中は年金が支払われ、その後は被保険者が生きている限り、一生涯年金を受け取ることができます。
この場合、被保険者が生きていれば本人が受給手続きを行い、亡くなった時には遺族(例えば障害のないきょうだい)が年金の停止手続きを行う、という仕組みなのかなと思いました。
ただ、ここでもう一つ気になる点が出てきました。
「受取人が生きている場合、停止手続きは受取人自身が行うのでは?」ということ。
ネットでいろいろ調べてみましたが、保証期間を過ぎてから被保険者が亡くなった際、誰が停止手続きをするのか、明確に書かれた情報は見つけられませんでした。
私自身、保険分野は得意とは言えず、FP資格を取得した際も保険と税制の分野には苦戦した記憶があります。
それでも、こうした学び直しの中で、制度の仕組みや実務上の細かな課題に改めて気づくことができるのは大きな収穫です。
「親なきあと問題」は、制度や商品、そして家族の想いが複雑に絡み合うテーマです。
これからも一つひとつの疑問を丁寧に掘り下げながら、実務に活かせる知識として整理していきたいと思います。