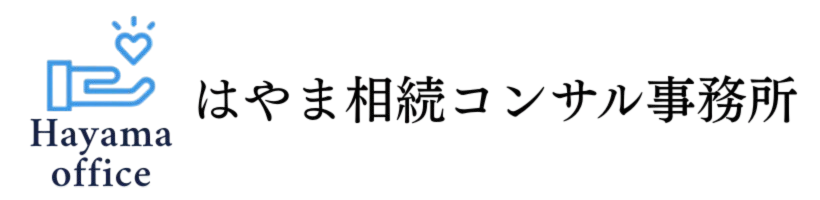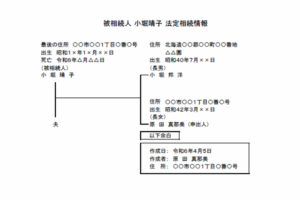2週間前のブログで、争族を防ぐための対策の一つとして「遺言書」について取り上げました。
今回は、そのきっかけとなった話をご紹介します。
知人Aさんの話
Aさん(仮名)はシングルマザーで、息子さんが2人います。
兄弟仲は一見普通に見えるものの、Aさんを介さないと直接の連絡はないのではないかという状態だそうです。
ある日、次男がAさんにこんなことを言ったとか。
「知ってる人のおじいちゃんが亡くなった時、遺言書がなくて兄弟でもめたらしいよ。
だから遺言書は書いといてね。」
Aさん自身も、息子たちの関係を見て「自分がいなくなった後、財産分与でもめるかもしれない」と感じており、何らかの対策をとる必要性があると思っていました。
Aさんはまだ50代ですが、「年金を受け取る頃には遺言書を作ろう」と考えているそうです。
贈与と保険でバランス調整
最近、Aさんは次男に「直系尊属からの住宅取得資金の贈与非課税制度」を利用して資金援助をしました。
理由は明確で、「お金があるうちに支援しておきたい」という思いからでした。
孫たちが成人する頃に援助できるお金が残っている保証はないからと。
さらに、長男にも配慮し、贈与額と同額の終身保険を契約。
受取人を長男に設定することで、結果的に公平性のバランスを取る形になっています。
金額も非課税枠の範囲内に収まっており、相続税の心配もありません。
Aさんは半ば思いつきで保険の契約をしたそうですが、仮に相続時、不動産の評価額が金融資産を上回る状況になり、長男自身の金融資産があまりなかったとしても、保険金の一部を代償金として次男に支払うことができるため、間違った判断ではないと説明しました。
Aさんの遺言書の内容(案)
Aさんが考えている遺言書の内容は次のようなものだそうです。
- 今後は近くに住む長男の世話になる可能性が高く、祖父母の墓の管理も引き継いでもらうことになるため、長男に少し多めに残したい
- 不動産は不動産に詳しい長男に相続させるが、代わりに時価相当額の半額を次男に支払う
死亡保険金については、そもそも「相続財産」には含まれないため、遺言書では触れないとのことでした。
遺言書を書く時は専門家に相談を
私はAさんに、「実際に遺言書を書く前に、内容に法律的な問題やおかしい点がないか、専門家に相談した方がいい」と伝えました。
遺言書は書けば終わりではなく、将来も有効に機能させるためのメンテナンスが必要です。
私自身も、60歳を迎えたら5年に一度のペースで内容を見直していこうと思っています。
今のうちからどんな遺言を作るか考え、相続診断士会で知り合った士業の先生にも相談する予定です。
遺言書は、家族構成や財産の内容、思いの変化に合わせて、定期的に見直すことで精度の高い遺言を残すことができ、争族を未然に防ぐことにつながると考えています。